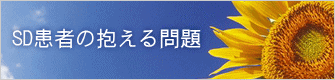
◆
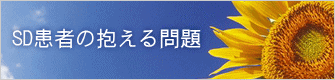
◆
一般に緊張によって声が詰まったり、震えるということは、誰にでも経験があることで、おそらくそれ自体は特に異常があるという事にはならないでしょう。痙攣性発声障害を持つ人の中には、自分が発声障害を持っているという自覚のない人もいます。それは、「声が出しにくい」という状態が常に一定のものではなく、場面によって症状が異なることから、自覚がうながされにくいということが考えられます。多くの痙攣性発声障害を持つ人は、「特に緊張した場面になると声が出しにくい」といいます。そして、声を出すということの過剰な意識化や、人前ではうまく声が出せないという数々の失敗経験が、痙攣性発声障害において、しばしば問題となってくる二次的障害を引き起こしてしまいます。つまり、発声障害という現象そのものと、声が思うように出せないという精神的苦痛によって様々な形として二次的障害は引き起こされ、より一層症状を悪化させてしまうと考えられます。 また、痙攣性発声障害においては周囲の人々の理解が得にくいということが大きな問題となります。自覚的にも、障害に対する意識が乏しいわけですから、周りの人々が発声障害であると認識することは、一層困難な状態にあると考えられます。「痙攣性発声障害」という認識がないばかりに、周囲の人々は「なぜ、普通に声が出せないのか?」という疑問を投げかけます。「もっと、力を抜けばいい」「もっと、大きな声を出すように」など、いろいろなアドバイスをくれるかもしれません。けれども、痙攣性発声障害が、実はそうした「コントロールが難しい」障害です。本来であれば、有り難い周囲の人たちのそうしたアドバイスは、痙攣性発声障害を持つ人にとっては、障害に対する無理解を突きつけられることに他ならないでしょう。声の震えは痛みを伴うものではなく、常に症状が表面化しているわけではありませんから、患者さんは、声が出しにくい時があるということに対して、すぐに病院で診てもらうという発想を持てないかもしれません。たとえ医療機関へと患者さんが足を運ぶことができても、痙攣性発声障害として、正しい診断を受けることができるかどうかは定かではありません。場面によって症状が表面化したり、しなかったりする痙攣性発声障害は、往々にして心因性ばかりが取り沙汰され、音声障害であるという診断がされにくい障害のようです。現在のところ、痙攣性発声障害と診断された患者さんの多くは、この診断名を得るまでに、複数の病院を転々としてきているのです。 |
| ◆ |
 |